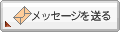› 仲村清司の沖縄移住録@2018 › 特別公開! 宮台真司さんの「あとがき」
› 仲村清司の沖縄移住録@2018 › 特別公開! 宮台真司さんの「あとがき」2014年09月18日
特別公開! 宮台真司さんの「あとがき」
版元の許可を得て
『これが沖縄の生きる道』
(宮台真司+仲村清司著・亜紀書房)
の「あとがき」を特別に全文掲載します。

http://www.amazon.co.jp/dp/4750514152/
あとがき:
〈世界〉は確かにそうなっている 宮台真司
【祭りの条件から見た沖縄】
沖縄に来るようになってまだ日も浅い二〇年ほど前、旧盆の久米島に渡った。この島は琉球の中でもとりわけ死の匂いが濃い。もちろん久米島守備隊住民虐殺事件に象徴される戦史を遡れる。当時の私は戦史もろくに知らぬまま、ただ死の匂いに敏感に反応していた。
鍾乳洞でのことだ。侵入禁止の札があっても先に進む癖のある私が、ふと足下を見ると、白くなった炭の燃え滓のようなものが一面に広がっていた。懐中電灯で照らすと白骨だった。さらに進むと無数の頭蓋骨が転がる広場に出た。長く使われてきた風葬の墓地だった。
その夜、八時を過ぎた頃、散歩していたら祭りに遭遇した。旧盆に琉球各地で行われるエーサーだった。小さな広場で見物人は五〇人もいない。地元の人だけで踊り、地元の人だけで見る。私が浮いていたのか、すぐに「ナイチャー(本土の人)ですか」と声を掛けられた。
男がパーランクーを叩き、女が手踊りして、ぐるぐる回る。派手さはないのに私は酔った。青森のねぶた祭り、熊野の火祭り、土佐のよさこい祭り、諏方の御柱祭り、全国の祭りを見てきた私がそれまでで一番酩酊した。昼間の白骨や頭蓋骨は酩酊の準備だったのだ。
伝統的な祭りには私たちが失いがちな前提がある。①同じ共同体に属し多くの前提を共有するという共属意識。②共通の過去に支えられているとの時間的シェア感覚。③循環する農耕的時間感覚。④祭りの準備にかかる手間暇。⑤トランスを導く反復的身体挙措など。
昨今でも祭りめいたものがある。三〇年以上前からのコミケット、一〇年前のオフ祭り(折り鶴オフなど)、最近ならニコニコ超会議。だが①共属意識、④祭りの準備、⑤トランス的反復挙措は辛うじて調達できても、②時間的シェア感覚、③循環的時間感覚は難しい。
私たちは過去を忘れることで今を生き(②)、自然が決めた時間割の中でしか動けないという感覚を忘れて今を生きる(③)。だから共属意識(①)が調達できても、代替の効かない時間のリソース(②)、代替の効かない自然のリズム(③)に軛されているとの意識はない。
だから共属意識――「われわれ」意識――に深みがない。共同体の自由を不自由へと反転することで〈感謝〉を経験する契機も、不自由を自由へと反転することで〈解放〉を経験する契機も乏しい。昨今の祭りめいたものは、拡散的で、緩く、眩暈感が限られている。
畢竟、これらは〈社会〉のイベントに過ぎず、〈社会〉の外=〈世界〉を開示しない。〈社会〉の外に戦慄して今に〈感謝〉し、〈社会〉の外に踏み出して今から〈解放〉されるという、祝祭=〈世界〉との接触契機がない。それゆえの深さの欠落を、動員規模や仕掛けで埋めているだけだ。
伝統的な祭りが〈社会〉の外を開示する理由を理解すべく、宗教・神話・伝説・昔話・英雄譚の関係を整理しておこう。「宗教」とは、前提を欠いた偶発性(なぜ世界はあるのか、なぜ不幸が襲うのか等)を無害化して受け入れ可能にする装置。「宗教」の内側に「神話」がある。
「神話」とは神(人ならざる存在)を主人公とするお話で、神が作ったというジェネシス(創世神話)を用いて、共同体が孕む偶発性を、必然性へと変換する機能を持つ。具体的には、なぜ世界は、人類はあるかというWHYに対し、HOW(経緯)によって答える形式を有する。
「伝説」とは人(神ならざる存在)を主人公とするお話で、共同体が孕む偶発性を、過去の特別な偶発性と結びつける機能を持つ。例えば共同体が(他の場所でもいいのに)なぜこの地にあるのかを、例えば、勇者が嵐の中で漂着したとの出来事から理解したりする。
「昔話」(寓話)とは人を主人公とするお話で、〈世界〉や〈社会〉が確かにそうなっているという納得を供給する機能を果たす。例えば「花咲か爺さん」であれば「正直であることが最後には見合う、社会とはそうなっているのだ」との納得をもたらしたりする。
最後に「英雄譚」だが、これは神話と伝説が交わるポイントに位置する。主人公は常人にない力を持つが、神ではないがゆえの不完全さも帯びている。まことに不思議なことに、主人公が今述べた性質を持つ英雄譚は、世界中どこでも共通の展開パタンを持つのである。
(1)王の血筋/不吉な予言/九死に一生/親との死に別れなどの「印付き存在」が、(2)魔物の退治/王の殺害といった「障害克服」を経て、(3)王妃と結婚/王に即位などの「幸福劇」ないし死/追放の「悲劇」で終わるが、(4)後には我々が知る社会の枠組が残る。
英雄譚は、機能的にも神話と伝説の中間にある。一方で、英雄による「障害克服」が、共同体の偶発性を必然性に転換する機能を与える。他方で、英雄以前にも、混乱した世界や社会があり、英雄譚自体はそもそも〈世界〉がなぜ存在するのかについて一切答えない。
どれもお話のパタン自体は童話やアニメやゲームに頻出する。だが、神の振る舞いで偶発性を必然性へと転換される共同体がなければ、神話は神話でなく、英雄の振る舞いで力と枠組を与えられる共同体がなければ、英雄譚は英雄譚でない。我々はどちらも知らない。
だから我々内地の人間の多くは本来の祭りを知らない。祭りは元々、神話・伝説・英雄譚と結びついている。というか、これらを再活性化させて、慣れ親しんだ事物が本来は「ありそうもない」事物であることを知らしめるものだ。だから祭りが〈社会〉の外を開示する。
内地から沖縄に来た者は、長く関わる内に、冒頭に紹介した如く〈社会〉の外が開示され、〈世界〉からの訪れに接触する瞬間に、幾度か立ち会うことになる。京都で育った私は、幼少期の京都で、そうした瞬間に何度か出会った。それが沖縄との関わりを決定している。
そうした私のような内地人(ナイチャー)から沖縄がどう見えるのか。私は映画批評家でもあるので、沖縄事情に知ったかぶりをして恥を晒すのをやめて、あくまで映画を切り口として語れる範囲で、私が沖縄で体験してきたことを、断片を通じて指し示してみたい。
【「内宇宙」から見た沖縄】
沖縄を舞台にした映画を撮り続けてきた中川陽介監督は、沖縄に住みたいと思うのではない、沖縄の風景や街並みを見るとそれにふさわしいドラマを思いつくのだと、どこかのインタビューで語っていた。風景や街並みにふさわしいドラマがある。どういうことか。
中川監督『真昼ノ星空』(二〇〇六年)が答えを示す。希望を抱いて生きるのをやめた男がいる。暗殺者としての仕事場の台北と、隠れ家の沖縄を往復する人生である。希望を抱いて生きるのをやめた女がいる。仕事場の弁当屋と、一人住まいのアパートを往復する人生である。
男は隠れ家で癒される。女はアパートで癒される。永久の往復運動があり、交わらない二人だと見えたが、コインランドリーでの邂逅を機に、単純往復運動が不規則化する。男が勇気を奮って女を食事に誘う。すると男の隠れ家も女のアパートも異空間へと変容した。
男の隠れ家は、まるで女が食事に来るのを待ちかねていたかのような打って付けの場所に〝変貌〞する。女のアパートは、まるで独居の寂しさを強制するかの如き殺伐とした場所へと〝変貌〞する。そこでは、空間が、風景が、人の内面を察知し、如何ようにも変貌していく。
男は、台北では暗殺者であり、沖縄では恋する青年だ。台北では、名前のある不自由な存在だ。沖縄では名前を欠いた自由な存在だ。だから台北には不自由な風景が展開し、沖縄では自由な風景が展開する。空間の自由・不自由を中川監督は光と音を使って演出する。
台北には隅々まで照らし出す光がある。そこでは隠れられない。沖縄には眩しき光と深い闇のコントラストがある。光の中で深呼吸した後、闇の奥に隠れられる。台北では都会の街頭音が騒々しくざわめき、沖縄では街の中にいてさえ吹き抜ける風の音が耳元に届く。
人は風景から孤立した内面を持たない。台北の風景が男を暗殺者にし、沖縄の風景が男を恋する青年にする。〈風景が内面に浸透する〉。孤独な暗殺者が部屋を暗く不自由な隠れ家とする。恋する青年が同一の部屋を自由な宴の場とする。〈内面が風景に浸透する〉。
風景と内面が邂逅する場所であるがゆえに風景なのか内面なのか定かでない空間。それをSF作家ジェームズ・グレアム・バラードは「外宇宙」に対して「内宇宙」と呼ぶ。彼の作品は風景の変化が内面に引き起こすものを討究する実験だった。変化した内面がさらに風景を変容させる。
『真昼ノ星空』が沖縄を舞台にした従来作より優れているのは、映画に描かれた沖縄が「内宇宙」であることを明白にしたことだ。暗殺者の男にとって、沖縄は癒しの場だった。都会人にとってのリゾートと同じだ。都会に疲れ、リゾートで回復し、都会に戻るだけ……。
そうした往復運動は人を変えない。台北と沖縄を往来する男も変わらない。だが女との邂逅を機に沖縄は「外宇宙」から「内宇宙」に変貌した。〈風景が内面に浸透し、内面が風景に浸透した者〉は元の場所に帰れない。主人公が同じ姿で台湾に戻ることはもうない。
内面と風景が浸透し合う「内宇宙」を描くのに中川監督は沖縄を必要とした。光と闇が、風と海が、疾走と静寂が、匂いと肌触りがある……というだけではリゾートに過ぎないが、やがて人間との交流を契機に、沖縄に来た時にだけ出現する「自分の姿」を知るに至るのだ。
【幻想を可能にする現実】
沖縄を舞台にした出馬康成監督の『マブイの旅』(二〇〇二年)は私に大きな動揺をもたらした。それを見ることは、私自身の映画的記憶を遡行することであり、また私自身の現実的記憶を遡ることだった。映画的記憶は「夢想」に相当し、現実的記憶は「断念」に相当する。
東京でリストラされ、妻と娘に逃げられた男が沖縄に渡り、娼婦にホレる。娼婦は若いボクサーにホレている。ボクサーはヤクザのしがらみで八百長試合や運び屋をする。彼の起こしたトラブルで誘拐された娼婦を助けに、男は単身ヤクザのアジトに乗り込む――。
汚れても汚れない(世界を受け入れても無垢な)娼婦(少女)という記号。疲れた(世界を受け入れて汚れた)男が、全てを捨てて娼婦(少女)にアクセスし、彼女に受け入れられて救済されるというモチーフ……。これは、遠い映画的記憶を呼び覚ます象徴体系だ。
例えば日活ロマンポルノの、とりわけ石井隆脚本『天使のはらわた』シリーズ。『女高生・天使のはらわた』(一九七八年)、『天使のはらわた・赤い教室』(一九七九年)、『天使のはらわた・名美』(一九七九年)、『天使のはらわた・赤い淫画』(一九八一年)。ロマンポルノ終了後も、『ルージュ』(一九八四年)、『ラブホテル』(一九八五年)と続いた。
だが『マブイの旅』は、九〇年代に作られた『ヌードの夜』(一九九三年)や『天使のはらわた・赤い閃光』(一九九四年)と違い、古くさい印象を与えない。これは沖縄という舞台設定が関係している。東京を舞台にしては描けない「夢想」が、沖縄だからこそ可能になっているのである。
私は九〇年を挟む一〇年間のテレクラを北海道から沖縄までフィールドワークした。拙著『まぼろしの郊外』に書いたが、九〇年代前半、東京では「匿名的記号としてしか出会えない」のに、地方では「知らない人と昔からの知り合いみたく出会える」という違いが際立った。
その後、瞬く間に地方的作法が失われて東京化した。中学全共闘後に沖縄に渡った風俗ライターの故・東ノボル氏が、沖縄のテレクラにおける出会いコミュニケーションをヒントに「瞬間恋愛」の言葉を作り出したように、この地には本土で失われた作法が辛うじて生き残っていた。
『マブイの旅』は、風景を通じて、こうした違いの背景を沖縄を知らない人にも納得させる。そこには、オリエンタリズム的ないし観光文化主義的な視線に映る、どこまでも抜けるように青い空や海は出て来ない。そこにあるのは「明るい沖縄」ならぬ「暗い沖縄」である。
スクリーンに映るのは、古い色街・真栄原の風景であり、新しいモール街・北谷の風景であり、中北部の住宅地である。だが、白壁がハレーションを起こす寸前の微妙に露光過剰な画面や、モノの彩りの微妙な組み合わせが、独特の空気感を実に見事に再現している。
那覇のコンベンション・センターでの上映会にトーク出演した時に「私たちが生きている沖縄を描いてくれている」と年長世代の観客たちから絶賛を浴びた所以だ。この時に観客の念頭にあるのは、もちろん航空会社の沖縄キャンペーンに連なる観光文化主義的な映画である。
誤解してはならないが、『マブイの旅』に描かれるような人への異様に濃密なコミットメントや、それを経由した救済のごときものが、「現実」に沖縄に存在するのでは、ない。むしろ存在しない。東ノボル氏の「瞬間恋愛」を引き合いに出したのも、それゆえである。
東ノボル氏は、もし今後もこの人といられたなら……という「夢想」によって虚数的に盛り上がる通りすがりの体験を、「瞬間恋愛」と名付けた。『瞬間恋愛』が上梓された九四年に初めて会った際に、当時すでに「もう沖縄にしか残っていないかもしれない」と語っておられた。
要はこういうことだ。「現実」にはあり得ない(と「断念」した)「夢想」を抱くにも、実は「現実」の基盤が必要になる。その証拠に、『天使のはらわた』シリーズが「夢想」に過ぎないことは当初から誰もが知っていたが、今では「夢想」としてすら映画に描けないのである。_
出馬監督は、当初は新宿歌舞伎町を舞台にした脚本を沖縄を舞台に書き直すという工夫で、この問題を克服した。重要なことは、「現実」にありそうなことを描く工夫だったのではなく、「夢想」を可能にする前提としての「現実」を、描くための工夫だったことだ。
「夢想」を可能にする空気感と言い換えてもいい。登場人物たちの方言や、彼らが口遊琉球民謡、そして突如出現する北谷の観覧車やエーサー隊が、眩暈を惹起し、この眩暈が切り開く神話的時空で、「断念」した男の痛切な「夢想」が、初めてリアルに描かれるのだ。
【匂いのある町ではない】
映画監督E・Nに「パトリとは何か」と訊かれたことがある。彼は和歌山県の田舎出身で、地元が嫌で嫌で悶々としながら育ち、高校を卒業するや上京したらしい。そんな彼にとって、私が「パトリ」を巡る文章を量産するのが、長らく不可解でならなかったという。
ところが、故郷の同窓生と電話で話した機会に、かつて存在したものが次々失われたことを聞いたと言う。故郷に帰って、いつも侵入して泳いだ学校のプールが、厳重に管理されるようになったのを知った。「それがね、確かに欠落感を感じるんだ」と彼は述懐した。
昨今のノスタルジー・ブームの中で、実写であれアニメであれ頻繁に「匂いのある町」が描かれてきた。パトリとは「匂いのある町」のことか。そう彼は尋ねた。違うと私は答えた。旅をして「匂いのある町」に出会う。でもそこはあなたにとってパトリではないと。
コミュニケーションには共通前提がある。二人だけの共通前提もあれば、家族の、学校の、世代の共通前提もある。家族や世代を超えて町全体が一つの共通前提に包まれてあると感じる時、人は「匂いのある町」を見出す。「匂いのある町」は時には旅人を排斥しもする。
例えば沖縄のクラブでは、ジャズやラテンやヒップホップの別を問わず、しばしば島唄のフレーズと琉舞の動きに合わせてオ・キ・ナ・ワと発語される。その瞬間、空間は濃密な一体感に包まれる。それは心地よく、羨ましくも感じられるが、その一体感の中に私はいない。
私はベアード・キャリコットを引き、パトリとは人と土地が入替不能な関係を構成する際の人と土地の複合体だと述べた。第一の要素として、彼にとって重要な何かをする時に使う手段が、その土地でしか入手できない場合、入手困難の程度においてパトリに近づく、と。
コンビニ的な「役割とマニュアル」に媒介された便益はどこでも入手できるが、関係の履歴に裏打ちされた「善意と自発性」に媒介された相互扶助は、中国のような血縁ネットワーク社会と違って地縁が意味を持つ日本では、彼にとって特定の場所でしか得られない。
ところがそうした手段入替困難性に還元できない二つの要素がある。固有名と、身体性である。まず、私の固有名や、固有名と結びついた人格性が、コミュニケーションの前提になることが、パトリの要件となる。それは、老若男女を問わず誰もが理解できるだろう。
身体性の要素はそうはいかない。これは経験的にしか想像できない。登下校時や外遊びの際の動線、空間、文物、関係が、盲人にとっての杖のように身体化した状態。そうした互いの身体性が互いを組み込み合うことで生じる「われわれ」意識を、私は〈共同身体性〉と呼ぶ。
盲人にとっての杖のように身体化された場所ということであればどこにでも簡単に生じる。だが動線、空間、文物、関係をも含み込んで、互いが互いの身体性を前提として組み込み合うような場所は、簡単には見つからない。この第三要素まで含めたパトリは稀少だ。
学校のプールがかつての姿を失ったことを知って「確かに欠落感を感じるんだ」と述べたE・Nは〈共同身体性〉には反応している。巷で語られる入替不能性や固有名詞性にはさして反応しない彼が〈共同身体性〉に反応する。私個人にとっても最も重要な要素である。
マイケル・アリアス監督『鉄コン筋クリート』(二〇〇六年)では、第一の手段入替困難性、第二の固有名性だけでなく、第三の〈共同身体性〉においても、「宝町」がパトリにふさわしい場所として描かれていた。単なる「自分が尊重されるわれわれの町」を超えた「深み」だ。
〈共同身体性〉を帯びた町は「微熱感」を帯びて現れる。『希望の恋愛学』(二〇一三年、KADOKAWA/中経出版)に書いた通り、新宿や渋谷にもかつて「微熱感」があったが、九〇年代半ばに一挙に消滅した。仲村清司氏に裏路地を案内された今の那覇は「微熱感」を辛うじて残している。
パトリが観光文化主義的な「匂いのある町」ではないことを述べたが、微妙である。パトリには手段入替困難性・固有名詞性・共同身体性に加え、再帰性という成立要件がある。パトリは、手段入替困難性・固有名詞性・共同身体性へと単に「埋め込まれた」者の前に現れないのだ。
手段入替困難性・固有名詞性・共同身体性の軛から解き放たれた者が、従来は自明だった風景から引き離されたがゆえの欠落体験を埋め合わせるべく、「パトリ」の観念を再帰的に――自覚的選択対象として――立ち上げる。一九六〇年代に「望郷の歌」が流行した所以である。
まず、自明性の欠落体験があり、次に、それを埋め合わせるために再帰的に「教養」や「美」や「親密」が定立されるというのが、ヨアヒム・リッターからオド・マルクヴァートを経てニクラス・ルーマンやノルベルト・ボルツへと継承された「埋め合わせ理論」であった。
埋め込まれた視座と、再帰する視座とでは、「同じもの」が天と地ほどの差異を以て体験される。その意味で、沖縄のことを、沖縄に生まれ育った者だけが分かるとは言えない。沖縄から遠く離れて戻った者、沖縄に深い縁を持つが沖縄出身でない者にも、役割がある。
近代の時代にある以上、他の近代社会――例えば内地――とは違った沖縄の在り方を護るためにも近代的方法を採る必要がある。いったん近代の地平に出て選び直すことが「再帰性」だが、再帰的な視座を欠いた者には、どんな意味でも沖縄を護ることはできないだろう。
【出版に到る経緯と謝辞】
昨今の沖縄問題の半分は沖縄が悪いという内容の本を書きたい、と盟友の藤井誠二氏に言い続けてきた。そんな本を内地の人間が書いても無駄だぜ、と彼は諫めてくれた。だったら沖縄にだってそんなふうに思う人がいるはずだから探してくれ、と頼んだのが五年前のこと。
実際に探し出した人たちを、彼と一緒にインタビューさせてもらったが、何か足りない。そんな折の二〇一二年に上梓された仲村清司氏の『本音の沖縄問題』を読み、仲村さんしかいないと思った。藤井さんはインターネットの番組などですでに仲村さんと既知の間柄だったから、紹介してくれた。
やはり決定的だった。同じ学年で、同じ京都に所縁があり、ともにサブカルキッズであり(仲村さんは『琉神マブヤー』第一シリーズ制作に参加)、ともにハイティーンの頃に学園闘争に触れている。むろん二世とはいえ沖縄ルーツの方だから、否、正確には二世だからこそ、沖縄の歴史について実に豊かで多面的な評価ができる方だ。
藤井誠二氏は、そんな仲村氏を紹介してくれたことだけでなく、その前の数々のインタビューをアレンジしてくれたこと、その際に幾度も藤井さん宅に泊めてくれたこと、そして仲村さんとの対談の司会をしてくれたことなど、感謝しても感謝しきれないのである。
仲村さんは、思いの丈をぶつける私に、不愉快な思いをされることもあったに違いないのに、温厚な笑みを絶やさず、恐らく私の社会学的な知識を触発することを意図し、象徴的事例や史実を幾つも挙げていただいた。おかげで、社会学的にもかなり深い話ができた。
仲村さんに那覇スージぐゎー(裏路地)を案内していただいて驚いたのは、殺風景な国際通りの裏などにあるタイムマシンで転送されたみたいに時間が止まった場所の数々を庭のように自由自在に経巡るだけでなく、出会う猫を全匹識別して個体名で呼んでおられたこと。
黄色いカレーについてはいろいろ縁がある。妻と出会った時に最初に食べたカレーが「オリエンタルマースカレー」だったし、彼女の前で最初に歌ったのもそのCMソングだったし、彼女に初めて暗記力を披露したのも南利明の「スナックカレー」の口上だった。
そこでまた驚いたのは、仲村さんが、この黄色いカレーの仲間たちを、沖縄にある三〇〇の食堂で食べ尽くしたということ。そして「マースカレー」のMARSが、マンゴー・アップル・レーズン・スパイスの頭文字であるという、私が知らない蘊蓄を傾けて下さったことだ。
また、少し前まで若手建築家集団「クロトン」に所属し、ぼくの本の熱心な読者でもあられるフリーランスの建築家・普久原朝充さんには、対談の随所で関連する大量の資料や写真をiPadで見せていただき、凄く役に立った。とても感謝している。
那覇在住の仲村さん、那覇と内地の往復生活を続けている藤井さんのおかげで、沖縄を訪れるたびに楽しくて変な人たちと知り合えたのも、うれしかった。楽しくて変な人たちにはナイチャーも大勢含まれているが、お二人の「類が友を呼んだ」のか、沖縄という時空のせいか。
亜紀書房の小原央明さんには太田出版の論壇誌『atプラス』の編集をしておられた時に御世話になり、抜群に優秀な編集者として記憶に残った。だから今回の対談を出版していただける編集者を探していた時、遅れた申し出だったが、小原さんしかいないと思った。
小原さんは、知識を習得するスピードも、対談録音を文字起こしするスピードも、注釈を付けるスピードも、常人のワザではない。加えて記憶力が異常で、対談で触れられた事柄に関連する記述がどこにあったのか一瞬で思い出し、原稿にメモ付けしてこられるのだ。
そんな優秀な編集者だったので、仕事の遅い私はひどく煽られたが、とても楽しかった。おかげで、冷や汗ものだったものの予定通りに出版できた。小原さんが著作者の一人だと申し上げても少しも過言ではない。小原さんには今後もあれこれと御願いをさせていただきたい。
小原さんは誰かに似ていると思っていたのだが、何度かお話ししたことがある映像作家で、私が死ぬほど愛している写真家中平卓馬のドキュメンタリー『カメラになった男』を撮られた小原真史氏の実弟でいらっしゃった。中平といえば沖縄にも極めて縁が深い。奇遇である。
二〇一四年九月
『これが沖縄の生きる道』
(宮台真司+仲村清司著・亜紀書房)
の「あとがき」を特別に全文掲載します。

http://www.amazon.co.jp/dp/4750514152/
あとがき:
〈世界〉は確かにそうなっている 宮台真司
【祭りの条件から見た沖縄】
沖縄に来るようになってまだ日も浅い二〇年ほど前、旧盆の久米島に渡った。この島は琉球の中でもとりわけ死の匂いが濃い。もちろん久米島守備隊住民虐殺事件に象徴される戦史を遡れる。当時の私は戦史もろくに知らぬまま、ただ死の匂いに敏感に反応していた。
鍾乳洞でのことだ。侵入禁止の札があっても先に進む癖のある私が、ふと足下を見ると、白くなった炭の燃え滓のようなものが一面に広がっていた。懐中電灯で照らすと白骨だった。さらに進むと無数の頭蓋骨が転がる広場に出た。長く使われてきた風葬の墓地だった。
その夜、八時を過ぎた頃、散歩していたら祭りに遭遇した。旧盆に琉球各地で行われるエーサーだった。小さな広場で見物人は五〇人もいない。地元の人だけで踊り、地元の人だけで見る。私が浮いていたのか、すぐに「ナイチャー(本土の人)ですか」と声を掛けられた。
男がパーランクーを叩き、女が手踊りして、ぐるぐる回る。派手さはないのに私は酔った。青森のねぶた祭り、熊野の火祭り、土佐のよさこい祭り、諏方の御柱祭り、全国の祭りを見てきた私がそれまでで一番酩酊した。昼間の白骨や頭蓋骨は酩酊の準備だったのだ。
伝統的な祭りには私たちが失いがちな前提がある。①同じ共同体に属し多くの前提を共有するという共属意識。②共通の過去に支えられているとの時間的シェア感覚。③循環する農耕的時間感覚。④祭りの準備にかかる手間暇。⑤トランスを導く反復的身体挙措など。
昨今でも祭りめいたものがある。三〇年以上前からのコミケット、一〇年前のオフ祭り(折り鶴オフなど)、最近ならニコニコ超会議。だが①共属意識、④祭りの準備、⑤トランス的反復挙措は辛うじて調達できても、②時間的シェア感覚、③循環的時間感覚は難しい。
私たちは過去を忘れることで今を生き(②)、自然が決めた時間割の中でしか動けないという感覚を忘れて今を生きる(③)。だから共属意識(①)が調達できても、代替の効かない時間のリソース(②)、代替の効かない自然のリズム(③)に軛されているとの意識はない。
だから共属意識――「われわれ」意識――に深みがない。共同体の自由を不自由へと反転することで〈感謝〉を経験する契機も、不自由を自由へと反転することで〈解放〉を経験する契機も乏しい。昨今の祭りめいたものは、拡散的で、緩く、眩暈感が限られている。
畢竟、これらは〈社会〉のイベントに過ぎず、〈社会〉の外=〈世界〉を開示しない。〈社会〉の外に戦慄して今に〈感謝〉し、〈社会〉の外に踏み出して今から〈解放〉されるという、祝祭=〈世界〉との接触契機がない。それゆえの深さの欠落を、動員規模や仕掛けで埋めているだけだ。
伝統的な祭りが〈社会〉の外を開示する理由を理解すべく、宗教・神話・伝説・昔話・英雄譚の関係を整理しておこう。「宗教」とは、前提を欠いた偶発性(なぜ世界はあるのか、なぜ不幸が襲うのか等)を無害化して受け入れ可能にする装置。「宗教」の内側に「神話」がある。
「神話」とは神(人ならざる存在)を主人公とするお話で、神が作ったというジェネシス(創世神話)を用いて、共同体が孕む偶発性を、必然性へと変換する機能を持つ。具体的には、なぜ世界は、人類はあるかというWHYに対し、HOW(経緯)によって答える形式を有する。
「伝説」とは人(神ならざる存在)を主人公とするお話で、共同体が孕む偶発性を、過去の特別な偶発性と結びつける機能を持つ。例えば共同体が(他の場所でもいいのに)なぜこの地にあるのかを、例えば、勇者が嵐の中で漂着したとの出来事から理解したりする。
「昔話」(寓話)とは人を主人公とするお話で、〈世界〉や〈社会〉が確かにそうなっているという納得を供給する機能を果たす。例えば「花咲か爺さん」であれば「正直であることが最後には見合う、社会とはそうなっているのだ」との納得をもたらしたりする。
最後に「英雄譚」だが、これは神話と伝説が交わるポイントに位置する。主人公は常人にない力を持つが、神ではないがゆえの不完全さも帯びている。まことに不思議なことに、主人公が今述べた性質を持つ英雄譚は、世界中どこでも共通の展開パタンを持つのである。
(1)王の血筋/不吉な予言/九死に一生/親との死に別れなどの「印付き存在」が、(2)魔物の退治/王の殺害といった「障害克服」を経て、(3)王妃と結婚/王に即位などの「幸福劇」ないし死/追放の「悲劇」で終わるが、(4)後には我々が知る社会の枠組が残る。
英雄譚は、機能的にも神話と伝説の中間にある。一方で、英雄による「障害克服」が、共同体の偶発性を必然性に転換する機能を与える。他方で、英雄以前にも、混乱した世界や社会があり、英雄譚自体はそもそも〈世界〉がなぜ存在するのかについて一切答えない。
どれもお話のパタン自体は童話やアニメやゲームに頻出する。だが、神の振る舞いで偶発性を必然性へと転換される共同体がなければ、神話は神話でなく、英雄の振る舞いで力と枠組を与えられる共同体がなければ、英雄譚は英雄譚でない。我々はどちらも知らない。
だから我々内地の人間の多くは本来の祭りを知らない。祭りは元々、神話・伝説・英雄譚と結びついている。というか、これらを再活性化させて、慣れ親しんだ事物が本来は「ありそうもない」事物であることを知らしめるものだ。だから祭りが〈社会〉の外を開示する。
内地から沖縄に来た者は、長く関わる内に、冒頭に紹介した如く〈社会〉の外が開示され、〈世界〉からの訪れに接触する瞬間に、幾度か立ち会うことになる。京都で育った私は、幼少期の京都で、そうした瞬間に何度か出会った。それが沖縄との関わりを決定している。
そうした私のような内地人(ナイチャー)から沖縄がどう見えるのか。私は映画批評家でもあるので、沖縄事情に知ったかぶりをして恥を晒すのをやめて、あくまで映画を切り口として語れる範囲で、私が沖縄で体験してきたことを、断片を通じて指し示してみたい。
【「内宇宙」から見た沖縄】
沖縄を舞台にした映画を撮り続けてきた中川陽介監督は、沖縄に住みたいと思うのではない、沖縄の風景や街並みを見るとそれにふさわしいドラマを思いつくのだと、どこかのインタビューで語っていた。風景や街並みにふさわしいドラマがある。どういうことか。
中川監督『真昼ノ星空』(二〇〇六年)が答えを示す。希望を抱いて生きるのをやめた男がいる。暗殺者としての仕事場の台北と、隠れ家の沖縄を往復する人生である。希望を抱いて生きるのをやめた女がいる。仕事場の弁当屋と、一人住まいのアパートを往復する人生である。
男は隠れ家で癒される。女はアパートで癒される。永久の往復運動があり、交わらない二人だと見えたが、コインランドリーでの邂逅を機に、単純往復運動が不規則化する。男が勇気を奮って女を食事に誘う。すると男の隠れ家も女のアパートも異空間へと変容した。
男の隠れ家は、まるで女が食事に来るのを待ちかねていたかのような打って付けの場所に〝変貌〞する。女のアパートは、まるで独居の寂しさを強制するかの如き殺伐とした場所へと〝変貌〞する。そこでは、空間が、風景が、人の内面を察知し、如何ようにも変貌していく。
男は、台北では暗殺者であり、沖縄では恋する青年だ。台北では、名前のある不自由な存在だ。沖縄では名前を欠いた自由な存在だ。だから台北には不自由な風景が展開し、沖縄では自由な風景が展開する。空間の自由・不自由を中川監督は光と音を使って演出する。
台北には隅々まで照らし出す光がある。そこでは隠れられない。沖縄には眩しき光と深い闇のコントラストがある。光の中で深呼吸した後、闇の奥に隠れられる。台北では都会の街頭音が騒々しくざわめき、沖縄では街の中にいてさえ吹き抜ける風の音が耳元に届く。
人は風景から孤立した内面を持たない。台北の風景が男を暗殺者にし、沖縄の風景が男を恋する青年にする。〈風景が内面に浸透する〉。孤独な暗殺者が部屋を暗く不自由な隠れ家とする。恋する青年が同一の部屋を自由な宴の場とする。〈内面が風景に浸透する〉。
風景と内面が邂逅する場所であるがゆえに風景なのか内面なのか定かでない空間。それをSF作家ジェームズ・グレアム・バラードは「外宇宙」に対して「内宇宙」と呼ぶ。彼の作品は風景の変化が内面に引き起こすものを討究する実験だった。変化した内面がさらに風景を変容させる。
『真昼ノ星空』が沖縄を舞台にした従来作より優れているのは、映画に描かれた沖縄が「内宇宙」であることを明白にしたことだ。暗殺者の男にとって、沖縄は癒しの場だった。都会人にとってのリゾートと同じだ。都会に疲れ、リゾートで回復し、都会に戻るだけ……。
そうした往復運動は人を変えない。台北と沖縄を往来する男も変わらない。だが女との邂逅を機に沖縄は「外宇宙」から「内宇宙」に変貌した。〈風景が内面に浸透し、内面が風景に浸透した者〉は元の場所に帰れない。主人公が同じ姿で台湾に戻ることはもうない。
内面と風景が浸透し合う「内宇宙」を描くのに中川監督は沖縄を必要とした。光と闇が、風と海が、疾走と静寂が、匂いと肌触りがある……というだけではリゾートに過ぎないが、やがて人間との交流を契機に、沖縄に来た時にだけ出現する「自分の姿」を知るに至るのだ。
【幻想を可能にする現実】
沖縄を舞台にした出馬康成監督の『マブイの旅』(二〇〇二年)は私に大きな動揺をもたらした。それを見ることは、私自身の映画的記憶を遡行することであり、また私自身の現実的記憶を遡ることだった。映画的記憶は「夢想」に相当し、現実的記憶は「断念」に相当する。
東京でリストラされ、妻と娘に逃げられた男が沖縄に渡り、娼婦にホレる。娼婦は若いボクサーにホレている。ボクサーはヤクザのしがらみで八百長試合や運び屋をする。彼の起こしたトラブルで誘拐された娼婦を助けに、男は単身ヤクザのアジトに乗り込む――。
汚れても汚れない(世界を受け入れても無垢な)娼婦(少女)という記号。疲れた(世界を受け入れて汚れた)男が、全てを捨てて娼婦(少女)にアクセスし、彼女に受け入れられて救済されるというモチーフ……。これは、遠い映画的記憶を呼び覚ます象徴体系だ。
例えば日活ロマンポルノの、とりわけ石井隆脚本『天使のはらわた』シリーズ。『女高生・天使のはらわた』(一九七八年)、『天使のはらわた・赤い教室』(一九七九年)、『天使のはらわた・名美』(一九七九年)、『天使のはらわた・赤い淫画』(一九八一年)。ロマンポルノ終了後も、『ルージュ』(一九八四年)、『ラブホテル』(一九八五年)と続いた。
だが『マブイの旅』は、九〇年代に作られた『ヌードの夜』(一九九三年)や『天使のはらわた・赤い閃光』(一九九四年)と違い、古くさい印象を与えない。これは沖縄という舞台設定が関係している。東京を舞台にしては描けない「夢想」が、沖縄だからこそ可能になっているのである。
私は九〇年を挟む一〇年間のテレクラを北海道から沖縄までフィールドワークした。拙著『まぼろしの郊外』に書いたが、九〇年代前半、東京では「匿名的記号としてしか出会えない」のに、地方では「知らない人と昔からの知り合いみたく出会える」という違いが際立った。
その後、瞬く間に地方的作法が失われて東京化した。中学全共闘後に沖縄に渡った風俗ライターの故・東ノボル氏が、沖縄のテレクラにおける出会いコミュニケーションをヒントに「瞬間恋愛」の言葉を作り出したように、この地には本土で失われた作法が辛うじて生き残っていた。
『マブイの旅』は、風景を通じて、こうした違いの背景を沖縄を知らない人にも納得させる。そこには、オリエンタリズム的ないし観光文化主義的な視線に映る、どこまでも抜けるように青い空や海は出て来ない。そこにあるのは「明るい沖縄」ならぬ「暗い沖縄」である。
スクリーンに映るのは、古い色街・真栄原の風景であり、新しいモール街・北谷の風景であり、中北部の住宅地である。だが、白壁がハレーションを起こす寸前の微妙に露光過剰な画面や、モノの彩りの微妙な組み合わせが、独特の空気感を実に見事に再現している。
那覇のコンベンション・センターでの上映会にトーク出演した時に「私たちが生きている沖縄を描いてくれている」と年長世代の観客たちから絶賛を浴びた所以だ。この時に観客の念頭にあるのは、もちろん航空会社の沖縄キャンペーンに連なる観光文化主義的な映画である。
誤解してはならないが、『マブイの旅』に描かれるような人への異様に濃密なコミットメントや、それを経由した救済のごときものが、「現実」に沖縄に存在するのでは、ない。むしろ存在しない。東ノボル氏の「瞬間恋愛」を引き合いに出したのも、それゆえである。
東ノボル氏は、もし今後もこの人といられたなら……という「夢想」によって虚数的に盛り上がる通りすがりの体験を、「瞬間恋愛」と名付けた。『瞬間恋愛』が上梓された九四年に初めて会った際に、当時すでに「もう沖縄にしか残っていないかもしれない」と語っておられた。
要はこういうことだ。「現実」にはあり得ない(と「断念」した)「夢想」を抱くにも、実は「現実」の基盤が必要になる。その証拠に、『天使のはらわた』シリーズが「夢想」に過ぎないことは当初から誰もが知っていたが、今では「夢想」としてすら映画に描けないのである。_
出馬監督は、当初は新宿歌舞伎町を舞台にした脚本を沖縄を舞台に書き直すという工夫で、この問題を克服した。重要なことは、「現実」にありそうなことを描く工夫だったのではなく、「夢想」を可能にする前提としての「現実」を、描くための工夫だったことだ。
「夢想」を可能にする空気感と言い換えてもいい。登場人物たちの方言や、彼らが口遊琉球民謡、そして突如出現する北谷の観覧車やエーサー隊が、眩暈を惹起し、この眩暈が切り開く神話的時空で、「断念」した男の痛切な「夢想」が、初めてリアルに描かれるのだ。
【匂いのある町ではない】
映画監督E・Nに「パトリとは何か」と訊かれたことがある。彼は和歌山県の田舎出身で、地元が嫌で嫌で悶々としながら育ち、高校を卒業するや上京したらしい。そんな彼にとって、私が「パトリ」を巡る文章を量産するのが、長らく不可解でならなかったという。
ところが、故郷の同窓生と電話で話した機会に、かつて存在したものが次々失われたことを聞いたと言う。故郷に帰って、いつも侵入して泳いだ学校のプールが、厳重に管理されるようになったのを知った。「それがね、確かに欠落感を感じるんだ」と彼は述懐した。
昨今のノスタルジー・ブームの中で、実写であれアニメであれ頻繁に「匂いのある町」が描かれてきた。パトリとは「匂いのある町」のことか。そう彼は尋ねた。違うと私は答えた。旅をして「匂いのある町」に出会う。でもそこはあなたにとってパトリではないと。
コミュニケーションには共通前提がある。二人だけの共通前提もあれば、家族の、学校の、世代の共通前提もある。家族や世代を超えて町全体が一つの共通前提に包まれてあると感じる時、人は「匂いのある町」を見出す。「匂いのある町」は時には旅人を排斥しもする。
例えば沖縄のクラブでは、ジャズやラテンやヒップホップの別を問わず、しばしば島唄のフレーズと琉舞の動きに合わせてオ・キ・ナ・ワと発語される。その瞬間、空間は濃密な一体感に包まれる。それは心地よく、羨ましくも感じられるが、その一体感の中に私はいない。
私はベアード・キャリコットを引き、パトリとは人と土地が入替不能な関係を構成する際の人と土地の複合体だと述べた。第一の要素として、彼にとって重要な何かをする時に使う手段が、その土地でしか入手できない場合、入手困難の程度においてパトリに近づく、と。
コンビニ的な「役割とマニュアル」に媒介された便益はどこでも入手できるが、関係の履歴に裏打ちされた「善意と自発性」に媒介された相互扶助は、中国のような血縁ネットワーク社会と違って地縁が意味を持つ日本では、彼にとって特定の場所でしか得られない。
ところがそうした手段入替困難性に還元できない二つの要素がある。固有名と、身体性である。まず、私の固有名や、固有名と結びついた人格性が、コミュニケーションの前提になることが、パトリの要件となる。それは、老若男女を問わず誰もが理解できるだろう。
身体性の要素はそうはいかない。これは経験的にしか想像できない。登下校時や外遊びの際の動線、空間、文物、関係が、盲人にとっての杖のように身体化した状態。そうした互いの身体性が互いを組み込み合うことで生じる「われわれ」意識を、私は〈共同身体性〉と呼ぶ。
盲人にとっての杖のように身体化された場所ということであればどこにでも簡単に生じる。だが動線、空間、文物、関係をも含み込んで、互いが互いの身体性を前提として組み込み合うような場所は、簡単には見つからない。この第三要素まで含めたパトリは稀少だ。
学校のプールがかつての姿を失ったことを知って「確かに欠落感を感じるんだ」と述べたE・Nは〈共同身体性〉には反応している。巷で語られる入替不能性や固有名詞性にはさして反応しない彼が〈共同身体性〉に反応する。私個人にとっても最も重要な要素である。
マイケル・アリアス監督『鉄コン筋クリート』(二〇〇六年)では、第一の手段入替困難性、第二の固有名性だけでなく、第三の〈共同身体性〉においても、「宝町」がパトリにふさわしい場所として描かれていた。単なる「自分が尊重されるわれわれの町」を超えた「深み」だ。
〈共同身体性〉を帯びた町は「微熱感」を帯びて現れる。『希望の恋愛学』(二〇一三年、KADOKAWA/中経出版)に書いた通り、新宿や渋谷にもかつて「微熱感」があったが、九〇年代半ばに一挙に消滅した。仲村清司氏に裏路地を案内された今の那覇は「微熱感」を辛うじて残している。
パトリが観光文化主義的な「匂いのある町」ではないことを述べたが、微妙である。パトリには手段入替困難性・固有名詞性・共同身体性に加え、再帰性という成立要件がある。パトリは、手段入替困難性・固有名詞性・共同身体性へと単に「埋め込まれた」者の前に現れないのだ。
手段入替困難性・固有名詞性・共同身体性の軛から解き放たれた者が、従来は自明だった風景から引き離されたがゆえの欠落体験を埋め合わせるべく、「パトリ」の観念を再帰的に――自覚的選択対象として――立ち上げる。一九六〇年代に「望郷の歌」が流行した所以である。
まず、自明性の欠落体験があり、次に、それを埋め合わせるために再帰的に「教養」や「美」や「親密」が定立されるというのが、ヨアヒム・リッターからオド・マルクヴァートを経てニクラス・ルーマンやノルベルト・ボルツへと継承された「埋め合わせ理論」であった。
埋め込まれた視座と、再帰する視座とでは、「同じもの」が天と地ほどの差異を以て体験される。その意味で、沖縄のことを、沖縄に生まれ育った者だけが分かるとは言えない。沖縄から遠く離れて戻った者、沖縄に深い縁を持つが沖縄出身でない者にも、役割がある。
近代の時代にある以上、他の近代社会――例えば内地――とは違った沖縄の在り方を護るためにも近代的方法を採る必要がある。いったん近代の地平に出て選び直すことが「再帰性」だが、再帰的な視座を欠いた者には、どんな意味でも沖縄を護ることはできないだろう。
【出版に到る経緯と謝辞】
昨今の沖縄問題の半分は沖縄が悪いという内容の本を書きたい、と盟友の藤井誠二氏に言い続けてきた。そんな本を内地の人間が書いても無駄だぜ、と彼は諫めてくれた。だったら沖縄にだってそんなふうに思う人がいるはずだから探してくれ、と頼んだのが五年前のこと。
実際に探し出した人たちを、彼と一緒にインタビューさせてもらったが、何か足りない。そんな折の二〇一二年に上梓された仲村清司氏の『本音の沖縄問題』を読み、仲村さんしかいないと思った。藤井さんはインターネットの番組などですでに仲村さんと既知の間柄だったから、紹介してくれた。
やはり決定的だった。同じ学年で、同じ京都に所縁があり、ともにサブカルキッズであり(仲村さんは『琉神マブヤー』第一シリーズ制作に参加)、ともにハイティーンの頃に学園闘争に触れている。むろん二世とはいえ沖縄ルーツの方だから、否、正確には二世だからこそ、沖縄の歴史について実に豊かで多面的な評価ができる方だ。
藤井誠二氏は、そんな仲村氏を紹介してくれたことだけでなく、その前の数々のインタビューをアレンジしてくれたこと、その際に幾度も藤井さん宅に泊めてくれたこと、そして仲村さんとの対談の司会をしてくれたことなど、感謝しても感謝しきれないのである。
仲村さんは、思いの丈をぶつける私に、不愉快な思いをされることもあったに違いないのに、温厚な笑みを絶やさず、恐らく私の社会学的な知識を触発することを意図し、象徴的事例や史実を幾つも挙げていただいた。おかげで、社会学的にもかなり深い話ができた。
仲村さんに那覇スージぐゎー(裏路地)を案内していただいて驚いたのは、殺風景な国際通りの裏などにあるタイムマシンで転送されたみたいに時間が止まった場所の数々を庭のように自由自在に経巡るだけでなく、出会う猫を全匹識別して個体名で呼んでおられたこと。
黄色いカレーについてはいろいろ縁がある。妻と出会った時に最初に食べたカレーが「オリエンタルマースカレー」だったし、彼女の前で最初に歌ったのもそのCMソングだったし、彼女に初めて暗記力を披露したのも南利明の「スナックカレー」の口上だった。
そこでまた驚いたのは、仲村さんが、この黄色いカレーの仲間たちを、沖縄にある三〇〇の食堂で食べ尽くしたということ。そして「マースカレー」のMARSが、マンゴー・アップル・レーズン・スパイスの頭文字であるという、私が知らない蘊蓄を傾けて下さったことだ。
また、少し前まで若手建築家集団「クロトン」に所属し、ぼくの本の熱心な読者でもあられるフリーランスの建築家・普久原朝充さんには、対談の随所で関連する大量の資料や写真をiPadで見せていただき、凄く役に立った。とても感謝している。
那覇在住の仲村さん、那覇と内地の往復生活を続けている藤井さんのおかげで、沖縄を訪れるたびに楽しくて変な人たちと知り合えたのも、うれしかった。楽しくて変な人たちにはナイチャーも大勢含まれているが、お二人の「類が友を呼んだ」のか、沖縄という時空のせいか。
亜紀書房の小原央明さんには太田出版の論壇誌『atプラス』の編集をしておられた時に御世話になり、抜群に優秀な編集者として記憶に残った。だから今回の対談を出版していただける編集者を探していた時、遅れた申し出だったが、小原さんしかいないと思った。
小原さんは、知識を習得するスピードも、対談録音を文字起こしするスピードも、注釈を付けるスピードも、常人のワザではない。加えて記憶力が異常で、対談で触れられた事柄に関連する記述がどこにあったのか一瞬で思い出し、原稿にメモ付けしてこられるのだ。
そんな優秀な編集者だったので、仕事の遅い私はひどく煽られたが、とても楽しかった。おかげで、冷や汗ものだったものの予定通りに出版できた。小原さんが著作者の一人だと申し上げても少しも過言ではない。小原さんには今後もあれこれと御願いをさせていただきたい。
小原さんは誰かに似ていると思っていたのだが、何度かお話ししたことがある映像作家で、私が死ぬほど愛している写真家中平卓馬のドキュメンタリー『カメラになった男』を撮られた小原真史氏の実弟でいらっしゃった。中平といえば沖縄にも極めて縁が深い。奇遇である。
二〇一四年九月

Posted by 仲村清司 at 15:10│Comments(0)